どうも こんにちわ 今回は一級自動車整備士試験の自動車新技術の教科書(水色の教科書)のハイブリット車の章よりアトキンソンサイクルについて解説をしていきます。

独学で一級整備士試験に合格した私がアトキンソンサイクルについて解説をします。
一級の試験開始より一級の教科書が変わっていないないため(2019.7現在)今では当たり前となっている10年以上前の新技術を新技術として学びます笑
ハイブリット車に関しては確か20系プリウスあたりが教科書の題材として使われていたと聞きました
今ではハイブリットだけでなく乗用車全体に使われているアトキンソンサイクルについて解説をしていきます。
ページ
アトキンソンサイクルエンジンとは?

圧縮行程と膨張行程が独立して設定できる機構をもったもの
インテークバルブの開閉時期の調整によりこの機能が実現できる。

簡単に言えばインテークバルブの制御をうまいことすることで効率が良くなり結果燃費が良くなる仕組みです。
メリット
・吸気損失低減。
・エンジンの最高出力、回転数を低く抑えることができるので燃費がよくなる
・同排気量エンジンを搭載したガソリンエンジン車に対してco2の発生量を2分の1にすることができ、CO,HC,NOxの排出量を規制値の約10分の1に削減することができる
デメリット
デメリットに対する対策
高い出力が得られないというデメリットに対してハイブリット車のモーターを利用することで出力面をサポートすることができる。
具体的にやっていること
インテークバルブが閉じる時期を遅くして、圧縮行程が始まる初期はシリンダ内に吸入した空気を一部インテークマニホールドに戻し圧縮の開始を実質的に遅らせることで実圧縮比を高めることなく高い膨張比を得ることができる。
過去問の傾向
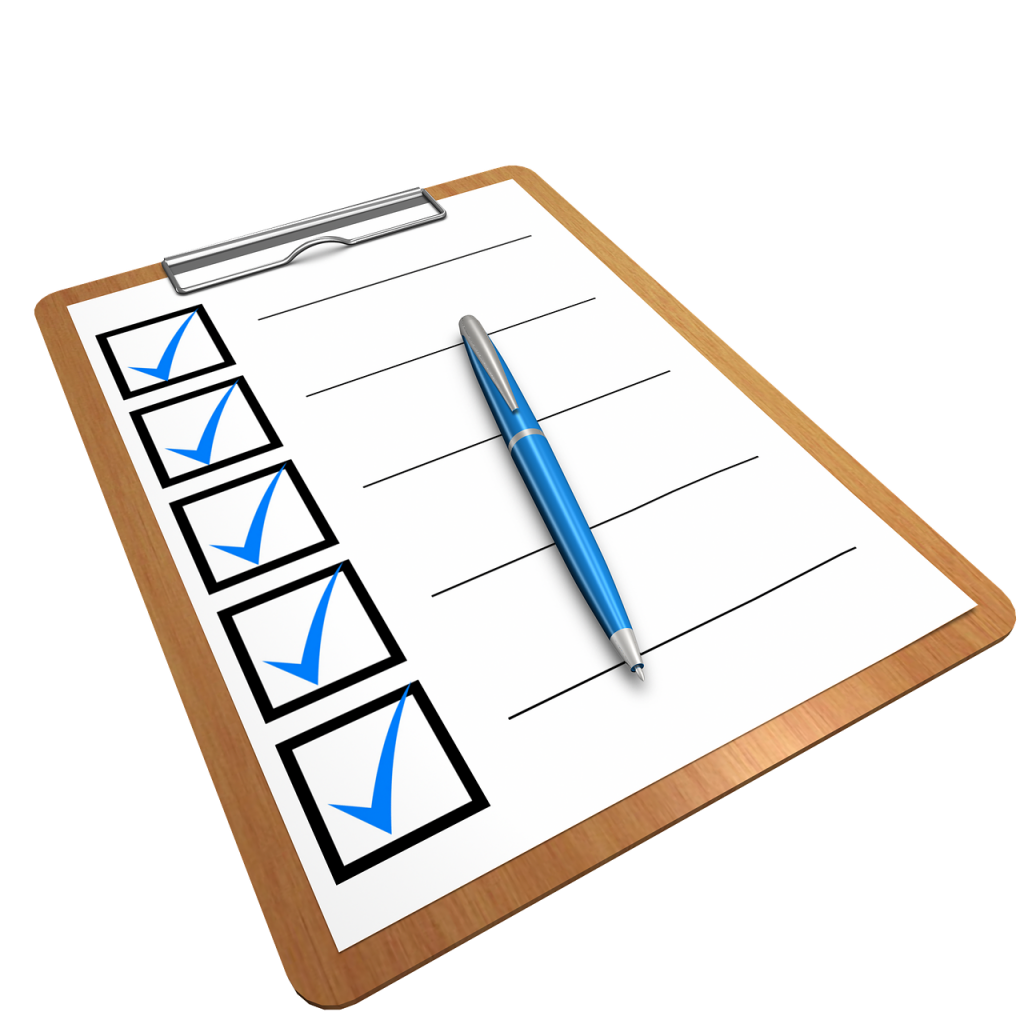
個人的には問題にめっさ出しやすい項目だと思うのですがハイブリット車の問題で1問しかでてこないのでそこまで過去問での出題傾向は少ないイメージです。
ですが上記の具体的にやっていることの太文字にしたところなんかを逆の意味にしたりして問題にすることは容易なのでこのへんは抑えておいた方がよいかと思います。
まとめ
今回は試験対策記事なのであえて深堀せずに解説をしました。
パワーが少ないところをモーターがカバーし効率がよくなり燃費が向上するアトキンソンサイクルの解説でした。最近出題されていないので毎年来年は出題されそうでこわいな・・と個人的には思っています。
おわり

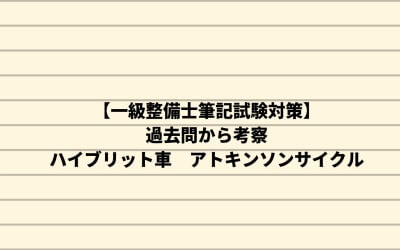


コメント